HIV予防といえばコンドームの使用が一般的ですが、近年はそれだけでは不安を感じる方も少なくありません。世界ではすでに新しい予防法として PrEP(プレップ) が広く利用され、日本でも注目を集めています。特に性風俗業界に従事する方を中心に利用が拡大し、海外から来た人々の間でも関心が高まっています。
本記事では、PrEPの効果や副作用、服用方法、費用や保険適用の有無、さらにはPEPとの違いまで網羅的に解説します。PrEPを検討している方や、正しい知識を身につけたい方にとって有益な情報をまとめました。
PrEP(プレップ)とは?
PrEP(プレップ)は、HIV感染を予防するための新しい方法として世界的に注目されています。従来の予防手段であるコンドームと並んで、リスクの高い人に推奨される選択肢となっています。
HIV感染を予防する曝露前予防内服(Pre-exposure prophylaxis)
PrEPは「Pre-exposure prophylaxis(曝露前予防内服)」の略称で、性交渉などHIVに感染する可能性のある行為の前から継続的に薬を服用しておくことで、ウイルスが体内に侵入しても感染を成立させないようにする方法です。
世界的な研究の結果、正しく服用すれば性行為によるHIV感染リスクを約99%減らせるとされています。
代表的な薬品名(ツルバダ・デシコビ)
PrEPに使われる薬剤は、もともとHIV治療薬として開発されたものです。日本や海外でよく使用されているのは次の2種類です。
- ツルバダ(Truvada):日本で認可されたHIV予防薬。エムトリシタビンとテノホビル・ジソプロキシルフマル酸塩の合剤。
- デシコビ(Descovy):比較的新しい予防薬。腎機能や骨への影響が少ないとされるテノホビル・アラフェナミドを含む。
これらはいずれも医師の診察と検査のうえで処方される薬であり、個人輸入や自己判断での使用はリスクが高いため注意が必要です。
世界・日本でのガイドラインと承認状況
PrEPはすでに国際的に認められたHIV予防法です。世界保健機関(WHO)は「すべてのHIV感染リスクが高い人に対し、PrEPを選択肢として提供すべき」とするガイドラインを公表しています。アメリカやヨーロッパでは、保険適用の対象となる国もあり、幅広く普及しています。
一方、日本では普及が遅れており、まだ限られた医療機関での自費診療が中心です。ツルバダはHIV予防薬として承認されているものの、保険適用はなく、費用は患者負担となります。今後、制度面での整備が進むことで、さらに利用しやすくなることが期待されています。
PrEPの効果と予防率
PrEPは、正しく服用することでHIV感染リスクを大幅に下げられることが世界的に証明されています。従来の予防手段であるコンドームに加え、より強力な予防策として導入が進められています。
HIV感染リスクを99%下げるエビデンス
複数の国際的な臨床試験により、PrEPをスケジュール通りに服用した場合、性行為によるHIV感染リスクを最大99%減少させることが明らかになっています。
効果が出るまでの期間(服用開始から約7日)
PrEPは服用を始めてすぐに効果を発揮するわけではありません。体内で十分な薬の濃度が安定するまでに時間がかかります。
一般的には、以下が推奨されています。
- 膣性交や注射薬の使用に対しては21日間の連続服用
そのため、計画的に使用を開始することが大切です。
コンドームとの違いと併用の必要性
PrEPはHIV予防には高い効果を持ちますが、他の性感染症(クラミジア、梅毒、淋菌など)や望まない妊娠は防げません。一方で、コンドームはこれらの予防に有効です。
そのため、HIV感染予防のためにPrEPを活用しながらも、以下の点に注意することが推奨されます。
- 性感染症や妊娠を防ぐためにはコンドームの使用を継続する
- 性交渉の相手が多い場合や不特定の場合は特に併用が望ましい
- 定期的な性感染症検査とセットでPrEPを利用する
PrEPとコンドームを組み合わせることで、より安全で安心な性生活を実現できます。
PrEPの服用方法
PrEPには大きく分けて「デイリーPrEP」と「オンデマンドPrEP」の2つの飲み方があります。生活スタイルや性行為の頻度に合わせて、自分に合った方法を選択できます。
デイリーPrEP(毎日1錠)
デイリーPrEPは、毎日決まった時間に1錠を服用する方法です。食事の影響を受けないため、自分にとって無理のない時間を決めて継続することができます。性行為の有無に関わらず服用を続けるので、急な機会にも対応できる点が大きなメリットです。安定した効果を得やすく、飲み忘れの心配も少ない方法といえます。
オンデマンドPrEP(性行為の前後に服用、男性限定)
オンデマンドPrEPは、性行為が予定される前後に服用する方法で、特に欧州で研究と導入が進んでいます。性行為の24時間前(遅くとも2時間前まで)に2錠を服用し、その後は24時間ごとに1錠ずつ、最後の性行為のあとさらに2回の服用を続けるのが基本的なスケジュールです。この方法は男性にのみ推奨されており、女性での有効性は十分に確認されていません。性行為の頻度が低い人や不定期な人に向いた方法といえるでしょう。
飲み忘れた場合の対処法
デイリーPrEPの場合は、飲み忘れに気づいた時点ですぐに服用し、翌日からは通常の時間に戻します。ただし、次の服用時間が迫っている場合は2錠まとめて飲むのではなく、1回分だけを服用します。
一方でオンデマンドPrEPでは、特に性行為前の2錠を忘れると十分な予防効果が得られません。そのため、スケジュール通りに服用することが重要となります。
PrEPは効果が非常に高い一方で、服用方法を守らなければ十分な予防効果を得ることができません。自分の生活リズムに合った方法を選び、無理なく続けられる体制を整えることが大切です。
副作用とリスク
PrEPは世界的に安全性が確認されている薬ですが、体質や服用状況によっては副作用が出ることがあります。多くの場合は軽度で一時的なものですが、長期的な影響にも注意が必要です。
短期的な副作用(吐き気・下痢・頭痛など)
服用を始めた直後には、以下のような症状が出ることがあります。
- 吐き気
- 腹痛や下痢
- 頭痛
- 皮疹
これらは数週間以内に自然とおさまるケースがほとんどで、日常生活に支障をきたすほど強い症状はまれです。
長期的なリスク(腎機能・骨密度低下)
PrEPを長期間にわたって服用した場合、腎臓や骨への影響が報告されています。
- 腎機能:一部の人で腎機能の低下が見られることがあります。
- 骨密度:わずかながら骨密度が下がる可能性がありますが、服用を中止すれば回復するとされています。
特に腎機能に不安のある方や50歳以上の方は、医師の管理のもとで慎重に利用することが推奨されます。
定期検査による安全管理(HIV・腎機能・B型肝炎)
PrEPを安全に続けるためには、定期的な検査が不可欠です。
- HIV検査:服用開始前と開始後1か月、以降は3か月ごとに実施
- 腎機能検査:原則12か月ごと。基準値が低い方や高齢者は6か月ごと
- B型肝炎検査:服用開始前に実施。感染がある場合は注意が必要
このような検査を受けることで、副作用の早期発見と安全な継続が可能になります。
PrEPの利用が広がる背景
PrEPは世界的に広がりを見せており、日本でも徐々に関心が高まっています。その背景には、特定のコミュニティや職業におけるHIV感染リスクの高さがあります。
性風俗業界における活用
性風俗に従事する人は、不特定多数との接触が避けられないため、HIVをはじめとする性感染症のリスクが高まります。PrEPを導入することで、従業者自身の感染リスクを下げると同時に、利用者への安心感にもつながります。予防を徹底する姿勢は、業界内での安全意識の向上にも寄与しています。
PrEPとPEPの違い
HIV感染を予防する方法としては、PrEP(プレップ)とPEP(ペップ)の2つがよく知られています。どちらも薬を使った予防手段ですが、使い方や目的は大きく異なります。
PrEP(感染前の予防)
PrEPは「曝露前予防内服」と呼ばれる方法で、HIVに感染する可能性のある行為の前から薬を飲んでおくことで感染を防ぐものです。あらかじめ服用して体内に薬の濃度を維持することで、ウイルスが侵入しても感染が成立しにくくなります。計画的に利用することで高い効果を発揮します。
PEP(感染リスク後72時間以内の予防)
PEPは「曝露後予防内服」と呼ばれ、HIVに感染したかもしれない行為のあとに行う緊急的な予防法です。感染リスクがある出来事から72時間以内に服用を始め、4週間程度の継続服用が必要になります。開始が遅れるほど効果は下がるため、迅速な判断と医療機関の受診が求められます。
どちらを選ぶべきかの目安
- 日常的にHIV感染リスクが高い人(性風俗従事者など) → 計画的に服用できるPrEPが推奨されます。
- 予期せぬリスクに直面した人(コンドームが破れた、不特定の相手との性行為、注射針の使い回しなど) → 緊急対応としてPEPを検討します。
このように、PrEPとPEPは補完関係にあり、日常の予防策としてはPrEP、万一の事故にはPEPと使い分けるのが現実的です。
PrEPの費用と保険適用
PrEPは高い予防効果が期待できますが、費用や保険適用の有無は利用を検討する上で大きなポイントとなります。ここでは代表的な費用相場と、日本での制度上の位置づけを整理します。
デイリーPrEP・オンデマンドPrEPの費用相場
PrEPは基本的に自費診療であり、服用方法によって費用が異なります。
- デイリーPrEP(毎日1錠):1か月分でおおよそ1〜2万円前後(ジェネリック薬を使用する場合)。
- オンデマンドPrEP(性行為の前後に使用):必要なときだけ服用するため、1回あたり数千円程度で始められるケースが多いです。
いずれも初診時にはHIVや腎機能、B型肝炎などの検査費用が加わるため、初回はやや高額になります。
先発品(高額)とジェネリックの違い
PrEPに用いられる代表的な薬には、先発品とジェネリックがあります。
- 先発品(ツルバダなど):1か月あたり10万円以上と非常に高額。長期利用が難しいという課題があります。
- ジェネリック(後発薬):同じ有効成分を含み、費用はおおよそ1〜2万円前後に抑えられます。品質を確認した上で利用すれば、続けやすい選択肢となります。
こうした事情から、日本国内の多くのクリニックではジェネリック薬を中心に処方しています。
日本での保険適用の現状と課題
現状、日本ではPrEPは保険適用外であり、すべて自費診療となっています。
一方で、アメリカや欧州の一部の国では公的医療保険や補助制度の対象となっており、利用が広がる要因のひとつになっています。
日本でも毎日数人が新たにHIVに感染している状況を踏まえると、今後は保険制度の整備や公的支援が課題となるでしょう。
費用の高さが利用のハードルになる一方で、ジェネリックの普及やオンライン診療の拡大によって、以前よりは手に取りやすくなっているのも事実です。
PrEPを始める前に必要な検査
PrEPは高い予防効果が期待できる一方で、安全に利用するためには服用開始前にいくつかの検査を受ける必要があります。これらの検査によって、既存の感染や持病を見逃さず、薬の副作用リスクを最小限に抑えることができます。
HIV検査
まず最初に行うのはHIV検査です。PrEPは「HIVに感染していない人」を対象とした予防薬のため、すでに感染している場合は使用できません。もし感染がある状態で服用を始めると、薬の耐性ウイルスが生じる可能性があるため、必ず事前に確認が必要です。
B型肝炎検査
PrEPに用いられる薬は、B型肝炎の治療薬としても使われています。そのためB型肝炎ウイルスに感染している人が自己判断で服用すると、かえって症状が悪化するリスクがあります。B型肝炎に感染しているかどうかを確認し、必要に応じて医師の慎重な判断のもとで対応することが大切です。
腎機能検査
PrEPは長期的に腎機能へ影響を与えることがあるため、服用開始前に腎臓の働きを調べておくことが推奨されます。検査の結果、腎機能に問題がある場合はPrEPの処方が見送られることもあります。服用を開始したあとも、定期的に腎機能をチェックすることで安全に継続できます。
よくある質問(FAQ)
PrEPは飲酒と併用して大丈夫?
PrEPは飲酒と併用しても問題ないとされています。アルコールが薬の効果を弱めたり、副作用を強めたりすることは確認されていません。ただし、飲酒量が多いと薬の飲み忘れにつながることがあるため、生活習慣に注意することが大切です。
PrEPはどのくらい続けるべき?
続ける期間は人によって異なります。HIV感染のリスクが高い状況にある間は継続が推奨されます。例えば、複数のパートナーとの性交渉が続く時期や、性風俗に従事している期間などです。リスクがなくなれば、中止を検討することも可能です。
PrEPをやめるときはどうする?
服用を中止する場合は、医師に相談するのが安心です。デイリーPrEPの場合、最後の性行為から少なくとも数日間は服用を続けるのが推奨されます。急にやめても問題は少ないですが、検査や今後のリスクを踏まえて判断することが望ましいです。
他の薬との飲み合わせは?
PrEPは多くの薬と併用できますが、一部の腎臓に負担をかける薬や抗ウイルス薬、抗がん剤などとは注意が必要です。持病で薬を常用している場合は、必ず医師や薬剤師に相談してから服用を始めてください。
まとめ|HIV予防の新しい選択肢としてのPrEP
効果とリスクを理解して安全に活用する
PrEPは、正しく服用すればHIV感染リスクをほぼゼロに近づけられる強力な予防法です。一方で、副作用や長期的なリスクも存在するため、必ず医師の管理のもとで、定期的な検査とあわせて利用することが重要です。
正しい知識と定期検査で安心して利用を
PrEPはあくまで「知識と管理」を前提にした予防薬です。飲み方を守り、定期的にHIV検査や腎機能検査を受けることで、安全に継続できます。正しい情報をもとに、コンドームの使用や性感染症検査と組み合わせて活用することで、より安心な性生活を実現できるでしょう。

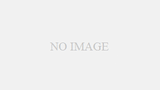
コメント